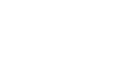コラム「異見と意見」COLUMN
子供達を親元へ、故郷へ返そう
時は4月。日本中で、企業が一斉に新入社員を迎える時である。当社もその企業規模からは多い6人もの新入社員を迎えた。その出身地は九州、四国、山陰、北海道など、全員が地方出身者である。当社は首都圏でしかビジネスを行っていないにもかかわらず、過去8年にわたって、新入社員は全て首都圏ではなく、地方社会から採用している。
親は子供が何歳になろうと、常に子供だと思っている。そしてどの親たちも、その手塩にかけて育てた子供が、成人して社会に巣立って行くことを祝いたい気持ちを持ちながら、一方では、活気があり、魅力的に見える遠い首都圏に就職して行くのを、寂しく見送ったに違いない。それは、子供を都会にとられてしまうような気持、あるいは都会生活に慣れ親しんだ結果、もう二度とこの田舎には帰って来ないのではないかという不安があるからであろう。
この様にして、数少ない子供たちが出て行った地方社会は、高齢化、過疎化が進み、残された親たちは寂しく老後を迎えることになる。
一方で進学や就職で首都圏に出て行った子供たちも、まだ温かい人情が残る地方社会とは違い、無縁社会とまで表現される人間関係が希薄な都市社会、厳しい成果主義ビジネス社会の中で必死に生きて行くことになる。多くのストレスを受け、時には孤独になり、故郷が恋しくなることも多いだろう。老齢の親のことが心配にもなるだろう。それでも再就職が難しい故郷に帰ることもかなわない。
今年の初め「限界集落株式会社」というNHKの土曜ドラマがテレビで放送された。その中で、地方社会に見切りをつけて都会に出て行った若い父親が、子供の残る故郷に戻って来る。その、たった一人の若い働き手が故郷に帰って来たというだけで、高齢化で停滞した雰囲気の故郷に動きが生じ、空気が変わり始め、地域社会に明るさが、活気が戻ってくるのを見た。一旦出て行ったとはいえ、そこで生まれ育った人が故郷に戻ってくることを、地方社会は心から願っている。このようなことが今日本中で起きている。
当社は10年前に、このような地方社会の実態を深刻に受け止める一方で、このような社会の変化に無関心で、ただ自社の業績にしか関心のない日本企業の経営実態に疑問を感じた。そこで、それまで首都圏の学生のみしか採用しなかった採用方針を全面的に転換して、それ以降は地方出身者にこだわった採用に切り替えてきた。そうして採用した地方出身の若者たちが、首都圏に出ることで視野を広げ、一人前のIT技術者に成長したら社員のままの身分で親元、故郷に返し、以降インターネットを活用してこれまで通り勤務することにより、先ずは育ててくれた親に安心してもらい、また自分自身も安心して働くという勤務態勢の開拓に挑戦するためである。この取り組みは、地方社会にまだ残っている思いやり、あるいは暖かい人情と言った、日本社会の伝統的な精神文化、生活文化を継承していってほしいと願うものでもある。
経済発展の目的は、そこに暮らす人たちの幸せを実現することにあるはずである。それにもかかわらず現実の社会では、ビジネス、経済発展のための活動が、多くのストレスを生み、人々の心は乱れ、人間らしささえも失わせているように感じられる。仕事の切れ目が縁の切れ目という無縁社会ではなく、人間らしい心を持った、人と人との暖かいつながりがある、そんな社会を取り戻したいものである。その為に、当社はそれが困難な取り組みであっても、地方出身者にこだわった採用に取り組み、新しい働き方、態勢の開発に挑戦して行く方針である。
しかしながら当社は、一社のみで社会を動かすことが出来るほどの大きな会社ではない。従って当社がいくら頑張っても日本社会全体を変えることはできないことは十分承知している。しかし“蟻の穴から堤の崩れ”という言葉もある。一人では何も出来ないかも知れないが、一人がやらなければ誰もやらない。たとえ小さな力であっても、それを継続すれば、それは徐々に広がり、大きな力になってくる。だからこのことがいかに困難であっても、多少のけがをしても、当社は泣き言など言わず、頑張り続けるつもりで取り組んでいる。
それだけではない。このような取り組みに挑戦する当社が好きで、全国各地から集まってくれた多くの社員たちの人生を考える時、彼らの貴重な人生の時間を、単なる企業業績、つまりお金の為だけに消耗させてはならないとも思う。社会に喜ばれる企業活動を通じて、社員がそこに勤めることが誇りに思えるような企業でありたいと思う。
そのような中で、当社の目指す経営に賛同して、その活動に参画するために、今年も多くの若者たちが入社してくれた。心から感謝して迎え、早く彼らを一人前のIT技術者に育て、首を長くして待っているであろう親元に、故郷に、一日も早く送り返してあげたいと思う。次の30年に向かっての新たな出発のこの時期、全社員が共に力を合わせて、この素晴らしい課題に挑戦することを誓い合いたいものだ。
(2015.04.06 記)